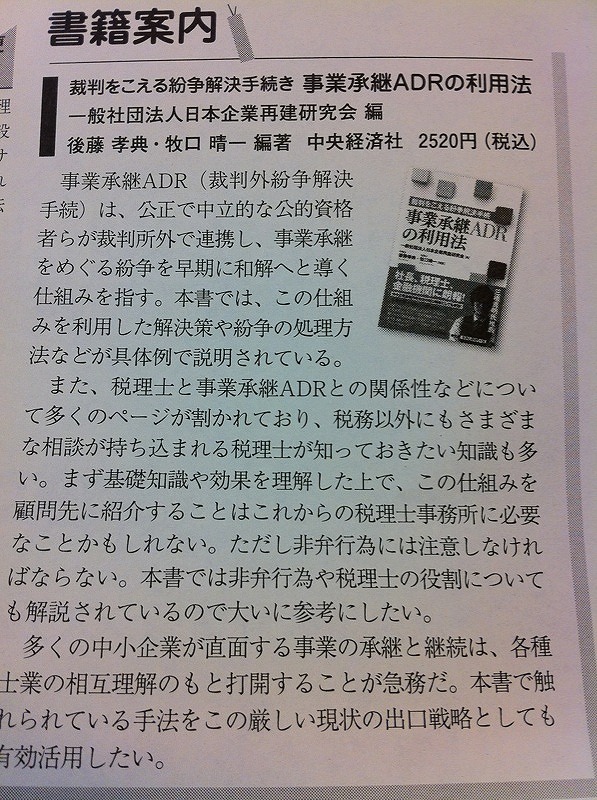最高裁平成25年9月4日決定は、父母が結婚していないからという理由で婚外子の法定相続分を嫡出子の二分の一とすることは、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこと」だから不当な差別だと断定し、婚外子の法定相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但し書きに規定は、法の平等を定める憲法14条に違反すると結論づけています。
子のほうでは選択の余地がない事で子を差別するのは違法だという論理は説得的ではありません。
最高裁は、この決定の前提として、法定相続分が均等でないことだけで憲法違反になりうるという、実に説得性のない論理に立ち、ある特定の大きさの遺産が嫡出子に帰属する場合と婚外子に帰属する場合と、その社会的意味は同じであると言う仮定の上に立っています。
しかし、この仮定は自明ではありません。最高裁もこの仮定を実はまったく論証していないのです。
特定の遺産が嫡出子に帰属する場合の社会的意味と婚外子に帰属する場合の社会的意味の違いを分析しなければ、ある特定の法定相続分帰属割合が、婚外子にとって不利益を及ぼすかどうかは判断できないはずです。ところがこの最高裁決定はそのような分析をまってやってもいません。最高裁は自分で出した決定が現実の社会で、どういうことを意味することになるのか、実はわかっていないのです。
私は遺産相続においては婚外子の法定相続分を嫡出子の半分とすることには合理性があると思います。その根拠は、財産には私的性質と公益的性質の二面があることに根ざしています。
財産の機能という観点から考えると、財産は所有者にとってのみ意味を持つものではありません。所有者の家族、所有者が経営する企業の従業員、その企業の仕入れ先、納入先のためにも必須不可欠な機能を持つっています。つまり、その財産がどのような性質の財産であるかによって、その財産の私的性質よりも公益的性質が顕著に現れることもあるのです。
公益的性質は、その財産が、小規模企業、中規模企業の生産活動の基礎である工場敷地、工場建物、生産設備、特許、知財など収益活動に貢献する財産である場合に顕著に表れます。
日本の企業は小規模企業、中規模企業だけではなく、トヨタ自動車、竹中工務店、サントリーが典型ですが、大企業も含め、同族企業の割合がきわめて高いのですから、遺産の公益性が現れやすい体質があるといえるのです。
婚外子にとって同族企業が自分にとっての遺産になっている場合を考えて見ますと、遺産は、その遺産が形成される過程で部分的にであれ、他の人たちと協同して、自己の労働をも提供した結果得られたものではありません。つまり自己の所得であるという性質はまったくありません。
しかも将来的にも、他の人々と協同してその遺産に自己の労働を加えて付加価値を向上させる機会さえ考えられない異物です。したがって、婚外子からみれば、故人となった経営者の財産は、自分の外部によそよそしく立ち上がっている物体にしかすぎませんから、婚外子にとって遺産は単に自分が私的に奪うべき財産にしかすぎません。
つまり、遺産は自分個人との私的な関係性しかあり得ようもないのです。
ところが、嫡出子にとっては、その遺産は、それが形成される過程に部分的にであれ、他の人たちと協同して、自己の労働をも提供した結果得られたものであるか、将来的には他の人々と協同してその遺産に自己の労働を加えて付加価値を向上させる機会が与えられる、いわば自己の血肉を分かち与えるべき財産です。
したがって嫡出子にとっては遺産は自分が奪う必要のない、協同して付加価値の向上に努めてきた仲間たちとともに共有すべき内なる財産ですから、その遺産は他の人々共に分かち合うべき公益的性質をもっているのです。
婚外子の法定相続分をどう考えるかと言う問題は、そもそも遺産というものが、それを手に入れたいと欲するひとにとって、自己の労働の対象となりうるか否かによって、まったく社会的意味が異なり、同一物でありながら、所得拡大にまったく貢献することがない場合と、所得拡大に貢献する有意義な場合とがあるのです。所得拡大に貢献しないのに、婚外子の法定相続分が嫡出子とそれと均等とすべき合理的理由はないといういべきでしょう。
特に、このような矛盾が顕著にあらわれる財物は、企業の株式です。数においては企業数のなかで圧倒的な割合を占める小規模企業、中規模企業においては、遺産はその故人が代表者であった会社の株式以外には、ほとんど見るべきものはないという場合が多いのです。
日本だけとは思いませんが、日本という国は、家族を核とした小規模企業が圧倒的に多いのです。農業や漁業、飲食店、八百屋、酒屋、それに医院、税理士、弁護士、司法書士などを含め、小規模企業が圧倒的な数です。
そして、それは時代おくれでも恥ずべきことでも決してなく、実は我が国が誇るべき国力の中心です。それだけに、遺産が株式である場合における婚外子の遺産分配請求の法的性質を検討しておく必要性は高いのです。